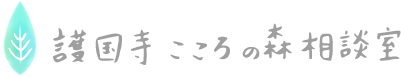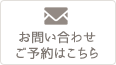分析主体のことば(AMPのHPから抜粋)
分析はブラックボックスのようなものなので、なかなか外からそのプロセスやなにが起こっているのかは分かりにくいと言われます。そのとおりだと思いますし、そのうえ、分析ではひとりひとり、まったく個別的なプロセスを辿るため、一般化するのがとても難しいとも思います。
それにかんして、AMP(世界精神分析協会)のHPに、「分析主体が説明する精神分析」というコーナーがあるのを見つけました(最初のページの下のほう)。分析主体(分析を受けている人)が、自身の分析にかんして簡潔に2分程度で語るというコーナーです。
そのコーナーでは何人かの証言が「分析主体のパロール(ことば)」としてオーディオ音源で掲載されており、じかに聞くことができるようになっています。
今回、ダニエルという名の人が語っているものを訳しました。タイトルは「分析家の選択」です。ダニエルがどのように分析家を選んだのかや、どんな分析となったのかなどを、かいま見ることができます。