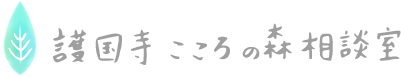精神分析家になるための資格試験は存在しないというのが、ラカン派精神分析の考え方です。分析家としての能力は、どんなペーパーテストや実技試験(?)によっても図れるものではない、ということです。
それでは人はどのようにして精神分析家になるのでしょうか。
ラカン派精神分析家団体(ECF、NLS、AMPなど)では、各自が精神分析を受けること(これは数十年に及ぶこともあります)や様々な研修を受けること、団体で認知されることなどが条件になります。
例えば室長の場合、分析を始めたのは1996年の秋からです。留学していた期間はもちろんですが、それ以外の時もできるだけ毎年渡仏して、滞在期間は日に何度も分析に通うようにして続けてきました。コロナ禍に入ってからは渡仏できず、電話で話を聞いてもらうこともありました。
とはいえ、今まで日本人で団体に入会できた方(=分析家として団体に認められる)はひとりもいなかったので、もう無理なのではないか、そもそも日本人は精神分析家になれる対象に入ってないのではないかと思うこともありました。分析家になれるのかどうかまったく保証のない中続けていくことは気持ちのなかで厳しいものがありました。それと同時に、自分のなかで謎となっているところ、分析されるべきところが残っている以上、やめることも考えられない心境でした。
分析家団体への入会が認められたのが2024年のことなので、分析を始めてから30年弱かかっている計算になります。日本人でもちゃんと認めていただけるのかと驚きましたし、もう一人同時に入会を果たした方と、喜び合いました。今後はもっと日本人の分析家が増えると思いますし、そのために尽力したいと思います。
人はどうやって精神分析家になるのかの話に戻ると、団体に認められ分析家として活動しながら、とりわけ「パス」と呼ばれる制度の認定を経ると、エコールの分析家 les analystes de l’École という名が与えられて、今の精神分析がどのようなものなのかを色々な大会で証言するという任務を3年間負います。「パス」に成功する人は毎年数人程度のほんの一握りなので、数多く分析家がいる中での分析家の「時の人」になるようなイメージです。
精神分析家になるための資格試験は存在しないことについて、精神分析家のジャック=アラン・ミレール氏の論文を訳しましたので、興味のある方はこちらの記事を参照してください。