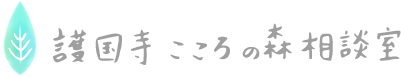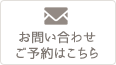ラジオ番組「精神分析のはなし」第14話ご紹介
フランス・キュルテュールのラジオ番組『精神分析の話』シリーズの第14話の訳になります。
フランスの精神分析家ジャック=アラン・ミレール氏が、精神分析のいろいろな事柄について、あまり専門用語を使わずに解説を試みている番組です。第14回目の今回は、「パートナーの発明」というタイトルがつき、17分ほどの内容です(2005年6月に放送)。欲望、欲動、愛についての考えが示されています。
試訳に関しましては,私の個人的な研究のために翻訳したものとなります。
※なお、この「パートナーの発明」は、以前このコラムで取り上げたものに若干の修正をくわえ、掲載しています。