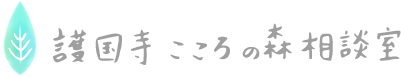ラジオ番組『精神分析のはなし』第10話 ご紹介
フランス・キュルテュールのラジオ番組『精神分析のはなし』シリーズの第10話の訳を載せます。
フランスの精神分析家ジャック=アラン・ミレール氏が、精神分析(ラカン派)について説明するシリーズです。今回は、全部で15分間ほどの内容になります。
話しているのは、「分析の終わりについて」、です。「パス」と呼ばれる手続きが紹介されています。少し複雑ですが、
渡る人=パスを行う人 passant
渡らせる人=パスを行う人の証言を聞く人 passeur
そして、このpasseurがパス審査会で、聞いたことを伝達する、・・という、独特な仕組みとなっています。
また、パスにおける振る舞いやあり方から、分析主体が本当に分析を終えたのかどうかが分かってしまう・・という例が5つ、紹介されています。
試訳に関しましては,私の個人的な研究のために翻訳したものとなります。