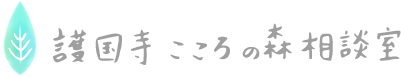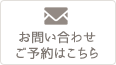ラジオ番組『精神分析のはなし第7話』のご紹介
フランス・キュルテュールのラジオ番組『精神分析のはなし』シリーズの第7話の訳を載せます。
今回はインタビュアーは登場せず、精神分析家ジャック=アラン・ミレール氏が、やさしく精神分析とはなにかを説明する番組です。全部で16分間ほどの内容になります。解釈=句読点をうつこと(ponctuation)についての説明に、重点がおかれています。
試訳に関しましては,フランス・キュルテュールのHPにAIによる転記つきで音源が載っていました。それを参考に私の個人的な研究の目的で訳したものになります。